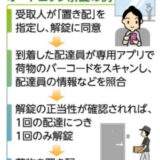世田谷区議会議員の福田たえ美です。
カームダウン・クールダウンスペース
感覚過敏の人に落ち着ける空間を官民で取り組んでいます。

光や音の刺激少なく/万博会場など、各地に取り組み広がる
「強い光が苦痛」「がやがやしている所が苦手」――。視覚や聴覚といった五感の刺激に対し、過剰に敏感となり、パニック発作など心身の不調を来す人がいる。こうした「感覚過敏」に悩む人たちが、外出先で、パニック発作などの前後に不安な気持ちや興奮を落ち着かせたりすることができるよう、音や照明を抑えた空間を設ける動きが官民で広がっている。
■発作前後など利用
通路の奥にパーティションで仕切られた3畳ほどの空間は、照明が絞られ薄暗かった。椅子に座ると、周囲の目線は気にならず、雑音も遠くに聞こえる程度だった。東京都港区役所本庁舎1階の福祉サービス担当窓口の近くに、区民の要望で昨年8月に設置された「カームダウン・クールダウンスペース」だ。
区担当者によると、「利用件数は限られているが、感覚過敏で悩む当事者から『とても助かる』と感謝されている」という。区議会公明党は9月定例会で同スペースのさらなる設置の推進を訴えている。
このような、外部の光や音などを遮断して休憩・避難できる空間づくりは、東京五輪・パラリンピックなどを機にバリアフリーの観点から注目され、空港や図書館など公共施設で整備され始めており、大阪・関西万博の会場内8カ所にも用意されている。
川崎市では、市役所本庁舎内に加え、スポーツ施設2カ所にも同スペースを開設。観戦中も、必要に応じて利用ができる。公明党の市議団が推進してきた。
一方、民間でも取り組みが始まっている。家電量販店大手の株式会社ヤマダデンキは神奈川県の17店舗で、店内の光や音量を弱める「クワイエットアワー」を月2回1時間程度、設けている。当事者からは「落ち着いた店内で買い物に集中できる」と好評だという。
■重い症状に苦しむ
「カームダウンスペースがあると安心して外出できるので、今後も増えてほしい」。こう語る北九州市在住の鈴木さゆりさん(59)の息子、勝浩さん(21)は幼少から聴覚の過敏症状が見られ、今も重度の症状に苦しんでいる。
光が苦手で家の中でも目をつむって歩き、部屋の電気を付けるスイッチの音に反応してパニックに陥ることも。家の外に出る場合はサングラスや騒音を和らげるイヤホンを装着するなど一苦労で、不安が絶えない。それだけに、同スペースの拡大などの進展に期待している。
■有用な薬なく治療困難
感覚過敏は現在、医学上では病気として扱われていない。有用な薬がなく、治療は難しい。当事者の数などの統計もないのが実情だ。原因については研究途中だが、国立障害者リハビリテーションセンター研究所の井手正和研究員は、脳内の神経伝達物質が関係しているという説が有力で、この物質の濃度が低いほど、感覚過敏が強くなる傾向があるとの認識を示している。
井手氏は「発達障がいの人に多いとされるが、健常者で症状が現れる場合もある。五感それぞれでさまざまな症状があり、個人差も大きく、把握が難しい」と説明する【表参照】。
■正しい発信必要
感覚過敏に悩む人は周囲の無理解でさらに苦しむことも多い。「行政が感覚過敏に対する理解を深め、正しい情報を発信していくことが求められている」と、井手氏は訴える。
■環境整備へ地方議員と連携/公明党医療制度委員長 秋野公造参院議員
感覚過敏の人が安心して社会生活を送れるようにするため、カームダウン・クールダウンスペースがいかに大切か。感覚過敏がよく見られる強度行動障がいの人が働きながら過ごす施設を訪問した時、実感した。
そこでは、同スペースが設けられていた。利用者が自傷や他害といった行動に出るかもしれないと自ら不安を感じたタイミングでその空間に入ると、情報が遮断できて心身を静められ、再び落ち着いて就労に戻れるという。
同スペースの設置といった環境調整を行うことで、強度行動障がいの人も平穏な日常生活を送れる。そう確信し、国会で障害福祉サービス事業者による環境調整への支援を繰り返し提案。その結果、2024年4月の報酬改定では環境調整が報酬の対象に位置付けられた。
強度行動障がいの人のほかにも、感覚過敏の人は少なくない。同スペース設置など、感覚過敏の人が安心して社会生活を送れるよう環境整備を進めていきたい。今後も党の地方議員と連携しながら取り組む決意だ。
■発作前後など利用
通路の奥にパーティションで仕切られた3畳ほどの空間は、照明が絞られ薄暗かった。椅子に座ると、周囲の目線は気にならず、雑音も遠くに聞こえる程度だった。東京都港区役所本庁舎1階の福祉サービス担当窓口の近くに、区民の要望で昨年8月に設置された「カームダウン・クールダウンスペース」だ。
区担当者によると、「利用件数は限られているが、感覚過敏で悩む当事者から『とても助かる』と感謝されている」という。区議会公明党は9月定例会で同スペースのさらなる設置の推進を訴えている。
このような、外部の光や音などを遮断して休憩・避難できる空間づくりは、東京五輪・パラリンピックなどを機にバリアフリーの観点から注目され、空港や図書館など公共施設で整備され始めており、大阪・関西万博の会場内8カ所にも用意されている。
川崎市では、市役所本庁舎内に加え、スポーツ施設2カ所にも同スペースを開設。観戦中も、必要に応じて利用ができる。公明党の市議団が推進してきた。
一方、民間でも取り組みが始まっている。家電量販店大手の株式会社ヤマダデンキは神奈川県の17店舗で、店内の光や音量を弱める「クワイエットアワー」を月2回1時間程度、設けている。当事者からは「落ち着いた店内で買い物に集中できる」と好評だという。
■重い症状に苦しむ
「カームダウンスペースがあると安心して外出できるので、今後も増えてほしい」。こう語る北九州市在住の鈴木さゆりさん(59)の息子、勝浩さん(21)は幼少から聴覚の過敏症状が見られ、今も重度の症状に苦しんでいる。
光が苦手で家の中でも目をつむって歩き、部屋の電気を付けるスイッチの音に反応してパニックに陥ることも。家の外に出る場合はサングラスや騒音を和らげるイヤホンを装着するなど一苦労で、不安が絶えない。それだけに、同スペースの拡大などの進展に期待している。
■有用な薬なく治療困難
感覚過敏は現在、医学上では病気として扱われていない。有用な薬がなく、治療は難しい。当事者の数などの統計もないのが実情だ。原因については研究途中だが、国立障害者リハビリテーションセンター研究所の井手正和研究員は、脳内の神経伝達物質が関係しているという説が有力で、この物質の濃度が低いほど、感覚過敏が強くなる傾向があるとの認識を示している。
井手氏は「発達障がいの人に多いとされるが、健常者で症状が現れる場合もある。五感それぞれでさまざまな症状があり、個人差も大きく、把握が難しい」と説明する【表参照】。
■正しい発信必要
感覚過敏に悩む人は周囲の無理解でさらに苦しむことも多い。「行政が感覚過敏に対する理解を深め、正しい情報を発信していくことが求められている」と、井手氏は訴える。
■環境整備へ地方議員と連携/公明党医療制度委員長 秋野公造参院議員
感覚過敏の人が安心して社会生活を送れるようにするため、カームダウン・クールダウンスペースがいかに大切か。感覚過敏がよく見られる強度行動障がいの人が働きながら過ごす施設を訪問した時、実感した。
そこでは、同スペースが設けられていた。利用者が自傷や他害といった行動に出るかもしれないと自ら不安を感じたタイミングでその空間に入ると、情報が遮断できて心身を静められ、再び落ち着いて就労に戻れるという。
同スペースの設置といった環境調整を行うことで、強度行動障がいの人も平穏な日常生活を送れる。そう確信し、国会で障害福祉サービス事業者による環境調整への支援を繰り返し提案。その結果、2024年4月の報酬改定では環境調整が報酬の対象に位置付けられた。
強度行動障がいの人のほかにも、感覚過敏の人は少なくない。同スペース設置など、感覚過敏の人が安心して社会生活を送れるよう環境整備を進めていきたい。今後も党の地方議員と連携しながら取り組む決意だ。
公明新聞 2025/10/08
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
世田谷区議会議員 福田たえ美
⚫︎福田たえ美 Twitter
</